オットリーノ・レスピーギ
作曲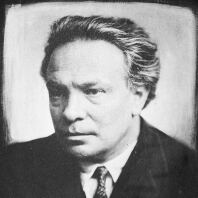
オットリーノ・レスピーギは「オペラの国」と呼ばれるイタリアにあって、あえて器楽音楽に取り組んだ作曲家世代の一人である。1916年に作曲した壮麗な管弦楽組曲《ローマの噴水》によって世界的な名声を確立し、初演から3年後の1920年には、その作品はベルリン・フィルの定期演奏会でも披露された。
レスピーギは1879年にボローニャで生まれ、1891年から地元の音楽院でヴァイオリンとヴィオラを学んだ。その後、イタリアの前古典派音楽を研究・出版していたルイジ・トルキや、作曲家ジュゼッペ・マルトゥッチに師事して作曲を学ぶ。学位取得前後にはオーケストラ奏者として活動し、サンクトペテルブルクの帝室劇場やモスクワのボリショイ劇場でのポジションを務めたのち、ボローニャ歌劇場管弦楽団の正式な団員となった。最初のロシア滞在中にはニコライ・リムスキー=コルサコフに学び、彼の卓越した管弦楽法は、レスピーギが1901年に学位を得た作品である「前奏曲、コラールとフーガ」にも色濃く反映されている。 1902年春には、ベルリンでマックス・ブルッフのレッスンを数回受けている。その後、ボローニャでアルトゥーロ・トスカニーニやフェルッチョ・ブゾーニと出会い、1905年には初のオペラ《エンツォ王》を上演、1906年以降は古楽の編曲にも取り組んだ。1908年からはベルリンで、エテルカ・ゲルスターの声楽学校において伴奏者として働き、同年10月12日にはアルトゥール・ニキシュ指揮ベルリン・フィルによってモンテヴェルディ《アリアンナの嘆き》の管弦楽編曲が演奏され、レスピーギは古楽編曲の名手として評価を確立した。1911年にボローニャ音楽院作曲科の教授に就任。その2年後、1913年にはローマのサンタ・チェチーリア音楽院に移り、1924年にはその院長に任命された。アルトゥーロ・トスカニーニの尽力もあり、レスピーギの作品は国際的に広く知られるようになった。1932年からはイタリア王立アカデミーの会員でもあったが、ファシスト党には入党せず、政権との個人的な関わりも持たなかった。レスピーギは1936年4月18日、ローマで没した。